もし猫の腎臓に疾患(異常)が見つかった場合には、まずその病気が治療できるものかどうかを考えます。たとえば腎臓で細菌感染が起こる腎盂腎炎があれば抗生剤で治療する、または、尿管に小さな結石が詰まって閉塞しているのであれば手術でその石を取り除く、などの原因治療を考えます。このように腎臓病の原因が明らかで、解決できるものであれば、その原因の解除を最優先にします。
ただ前述のとおり、腎臓は一度機能を損なうと回復しない臓器です。長い時間をかけて徐々に機能を損なってきた結果であったり、そもそもが治療できないような病気であったりした場合には、がんばって治すことよりもうまく付き合っていくことを考えなければなりません。
慢性腎臓の治療の目標は、腎臓病の更なる進行をさせないようにすること、いま猫を苦しめている症状があればその症状を緩和すること、腎臓病と一緒に付随して起こる様々な症状(合併症)を管理すること、これらをゴールとします。治らないものは仕方がないので、せめて病気を悪化させずに、なるべく猫が苦しまずに生活させてあげらることを考えていきましょう。
IRISステージ毎の大まかな治療の概要を見ていきましょう。IRISガイドラインでは以下のように記述されています(IRIS CKD ガイドライン2023)
ステージ1
脱水に気をつける(新鮮な水を常に飲めるように)
高血圧や蛋白尿などの合併症があれば治療
腎臓に副作用のある薬剤の使用はなるべく避ける
必要に応じて腎臓病療法食やミネラル管理(リン、カルシウム)を検討
ステージ2
(ステージ1 に追加して)
腎臓病療法食を検討
ミネラル管理(リン、カルシウム、カリウム)
ステージ3
(ステージ2 に追加して)
更なる脱水への注意
嘔吐、食欲不振、悪心に対する治療
貧血の治療を検討
更なるミネラル管理
ステージ4
(ステージ3に追加して)
栄養状態の維持
より積極的な脱水へ対応
更なるミネラル管理
病気が進行するにつれて、気をつけることや実施する治療が増えていきます。
現実的には全ての治療を行う必要はないと思います。たとえば毎日薬の飲まないといけないとして、それを猫が喜ぶかというと決してそんなことはないからです。薬を飲むのがそれほど苦にならない猫もいれば、すごく苦手な猫もいます。腎臓病の治療は基本的には長期戦です。1週間だけがまんして薬を飲むのと、一生涯薬を飲み続けるのでは訳が違います。
治療には当然費用もかかります。ものすごく高額な治療の割に、それほど効果が期待できない治療があったとして、敢えてそれを選択するかは飼い主ご家族によります。猫のためにどこまでお金をかけて良いと思っているかは個人の事情や考え方によります。がんばっても治らない病気を相手にする以上は、どの治療を選択して、どの治療を選択しないかは慎重に検討すべきです。
ただ治療によっては費用や労力の割に高い効果が期待できるものもあります。ぜひ今の腎臓病のステージや猫の性格を考慮したうえで、それぞれの治療の特徴や費用や労力を参考に、後悔のないように治療法を決定してもらいたいと願っています。
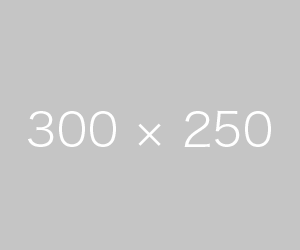
コメント