慢性腎臓病はごく初期から、いよいよ死が迫った末期まで、病気の進行とともに症状が悪化していくものです。この進行具合を分かりやすく区別したものをステージ(病期)と呼び、これを参考にすることで色々な役に立ちます。国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS、アイリスと読みます)という腎臓に詳しい獣医さん達により構成される団体があり、このIRISのメンバーで議論されて作られている慢性腎臓病のステージ分類が、私たち臨床獣医師の世界で最も一般的に参考にされていますので、こちらを紹介しましょう。
IRISステージ分類のメリット
このステージ分類を知ることで得られるメリット(=分かること)を挙げてみましょう。
- いま自分の猫がどれくらい腎臓病が進んでいるのか(現在地が分かる)
- いま日常生活でどんなことを気をつければ良いのか(生活上の注意点やフード選びの参考になる)
- いまどんな治療が検討されるのか(薬や点滴などの治療オプションの目安になる)
- あとどれくらい生きられそうなのか(予後の予測)
ステージは1から4まであります。ステージ1はまだ初期という判断になりますし、ステージ4が最も進行した状態です。
IRIS CKD ステージの大まかな解釈
IRISでは4つのステージを大まかに以下のように分類しています。
- ステージ1 腎臓に異常がみられる
- ステージ2 軽度の臨床症状もしくは症状なし
- ステージ3 様々な臨床症状が全身に発現
- ステージ4 集中治療が必要
徐々に病気が進行し、症状が悪化していく様子がなんとなくイメージできるでしょうか。ステージ1-2のうちは症状が軽度、もしくはまったくない。ステージ3以降は生活上の支障になるような影響が出てきて、ステージ4になれば生命の危機におよぶ状況になっていく、一般的にはこのように進行していきます。
実際の腎臓病診療
例えば、現在初期の腎臓病があるかもしれない子の場合だと、これらIRIS ステージを参考にすることで、現在のステージを知り、一般的にはどういう治療が必要な時期なのか、次は何を注意したら良いのか、次回の検診時期をどうしようかを考えるきっかけになります。
病院で診察(検査)を受ける
↓
慢性腎臓病がありそうかどうか?
↓
IRISステージを参照
↓
治療オプション、追加検査を検討
↓
次回の検査を予定
このような流れで腎臓病の管理を行っていきます。そうすると、慢性腎臓病の進行具合をより正確に把握することができますし、獣医療で標準的に推奨されている治療を検討することができます。
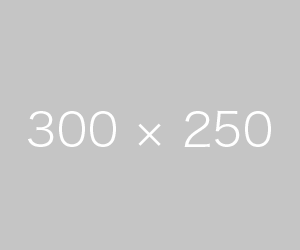
コメント